- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
「失われたれた30年」
かわさき技術士センター会長 磯村 正義
日本の一人当たりGDPが韓国に抜かれそうだという報道がありました(購買力平価ではすでに抜かれているという分析もあります)。
この30年間、日本の一人当たりGDPは横這いか微増に過ぎないのに、韓国初め多くのOECD諸国が右肩上がりの成長を続けています。
これには色々な要因があり、単純な問題ではないかもしれません。
しかし私が指摘したいのは、「地道なものづくりへの努力を怠っているのではないか」ということです。
バブルの時代の成功体験から、自ら技術を蓄積するより、金を払って他社から買った方が手取り早い、
ものづくりは労働力の安い海外でやればいい、あるいは、もともと品質がいいのだから、
多少検査データを改竄しても問題にはならない、等々枚挙にいとまがありません。
そしてこれらの傾向は、中小企業よりも、名だたる大企業の方に目立っていると感じています。
一方、日本の製造業は中小企業が支えていると言っても過言ではありません。
確かに雇用、賃金や設備投資の問題等、中小企業が抱えている問題は少なくありません。
しかしその中で愚直にものづくりの競争力を培い、小さくてもきらりと光るものを持っている、
そしてこれによって世界の中で自社の立ち位置を誇っている事例を少なからず知っています。
そこに、これからの日本の希望を見ることができるのではないでしょうか。
当センターはそのような中小企業の努力に敬意を払い、できる限りの支援をしていきたいと考えています
「情報革命と人材活用」
技術士(情報工学部門) 久田見 篤
講習会の最中に若い受講者の方がスマホを操作していました。
メールでもチェックしているのかと思い実習時間中にさりげなく見ると、
説明にあった技術用語をネットで調べている様子でした。
実習用のPCではなく個人のスマホを使っていたので講習会とは無関係の私用かと誤解してしまいましたが、
受講者の方は自分なりの方法で熱心に実習に取り組んでいた様子でした。
スマホの取り扱い方ひとつで若い世代との感覚ギャップを感じた出来事でした。
人類はこれまでに農業革命、産業革命、情報革命という3つの大きな社会構造革命を経験してきたといわれています。
情報革命は20世紀末のコンピュータとインターネットの利用から始まり、
大規模データー処理、仮想空間、AI技術などに取り組んでいる状況といえます。
社会構造革命の立上りには50年程度の急激な社会変化が伴うことを考えると、
情報革命の立上り時代に生きる我々にとって、世代間の感覚ギャップは今後も広がり続けると考えるのが良さそうです。
総務省の「2022年版情報通信白書」によれば、企業活動でDX(デジタル・トランスフォーメーション)へ取り組んでいる日本企業は約56%であり、
米国の約79%に比べて低い割合となっています。
また、DX推進の課題として、「人材不足」が約68%、「デジタル技術の知識・リテラシー不足)」が約45%と、日本企業は人材に関する課題が多く、
特に「AI・データ解析の専門家」は、米国やドイツと比べると不足状況が深刻であると分析しています。
企業の4大経営資源「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち、
「情報」に関しては、経営者の経験不足や人材不足などで取組が不十分と感じている場合も多いと思います。
一方で、2000年以降に生まれた人々が成人し、情報の専門家でなくても情報化に対して新しい感覚を持った人々が社会で影響力を持つ様になっています。
企業の「情報化」の取組みに関しても、経営者が新しい世代の人々の感覚を学び、意見を取り入れることが今まで以上に重要であり、
組織の情報化改革において新世代の人々に積極的に参画してもらうことは人材活用と人材育成の観点からも有意義であると思います。
「安衛法改正の対応について考える」
技術士(経営工学・総合技術監理部門)服部昌幸
労働安全衛生法(以下安衛法)は昭和47年に制定されました。制定後に労働災害は10年ほどで急速な減少を遂げています。 その後数多くの改正が行われました。改正は経営者と労働者に新たな負担を生じさせます。 今回は製造業に関する下記3点の事例を選び対応について考えてみました。
- リスクアセスメント実施の義務化:平成18年、リスクアセスメントが努力義務規定になり ました。重篤度と発生の可能性でリスクを評価するこの手法は広がりをみせて平成28年には化学物質のリスクアセスメントも義務化されました。
- 墜落・転落防止対策の強化:平成21年の改正で、墜落防止措置や作業開始前の点検等の義務化 がされました。平成31年には安全帯(墜落制止器具)がフルハーネス型に規制されています。
- 粉塵障害予防規則の改正:屋内のアーク溶接作業は、すでに粉塵作業として呼吸用保護具使用 義務がありましたが、平成24年には屋外でのアーク溶接も同様に使用義務になりました。
1. の法改正は、社会環境の変化への対応であり「一度あった災害を二度と起こさない」から
「未知の災害も予知して防ぐ」という時代の変化への対応です。
一方2. と3. は根絶や重篤度の軽減が難しいための規制強化です。
1. は労災の減少や起因によるもので納得できますが、2. の規制の強化は労働者への負荷が直接増すことから困難が伴います。
粉塵規則の改正で屋外作業で従来の「保護具なし」から「呼吸用保護具の着用」を義務づけられた溶接作業者からは
「なぜ今、粉塵なのですか?」の質問が出るなど抵抗され、管理者は作業者へ遵法の説得が必要になります
親しい小規模企業の社長さんとこうした法改正に対峙したとき重要なのは何か、という話し合いをしました。
重要なのは、「 ① 経営者の毅然たる遵法への姿勢、② 職場の作業者とのコミュニケーション」が結論でした。
遵法は義務です。
「① の姿勢は経営者の当然の自覚と覚悟です。② の作業者とのコミュニケーションは、
法規制は“自分達のため”とする意識の醸成には作業者との協調が必須であるからです」がその理由です。
この企業は社員30数人で法の規制外なのに敢えて2カ月に1回の安全衛生委員会を設け、
社長は出席者と意見を交わし安全意識を高めているとのことです。
経営者の意欲と労働者の意識が安全の根幹にあることを認識し、地道な努力を続けることが大切です。
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)
2022年度「KIIP公益財団法人川崎市産業振興財団」との共催(技術)セミナーを終了のご報告。

9/14(水)「業績向上につながる課題の選定と達成アプローチ~ISO9001と課題達成型QCストーリーの考え方を取り入れて~」 10/19(水)「電気自動車用二次電池の現状と将来~リチウム二次電池から、全固体電池、新型二次電池~」 11/16(水)「迫られる企業の環境取組~一人で悩まない 周りには情報や応援団がいっぱい~」 上記、Zoom オンラインセミナー(15:00~17:00)を実施致しました。 多くの皆様にはご参加いただき、ありがとうございました。今後とも、ご活用頂きたくよろしくお願いいたします。 |
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| ワンデイ・コンサルティング (無料) |
原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援します。最大3回可能です。 |
| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援。 |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/
NPO法人 かわさき技術士センター URL:http://www.n-kgc.or.jp/ E-mail: info@n-kgc.or.jp
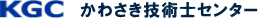
 技術支援ニュース
技術支援ニュース