- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
「政権交代とエネルギー政策」
技術士(機械部門) 磯村 正義
これまで民主党政権では原発ゼロを目指し、昨年末の総選挙では、
多くの政党が脱原発/卒原発を主張しましたが、安倍政権ではそれを見直そうとしています。
原発の是非はここではさておき、今後の日本のエネルギー政策のありかたについてちょっと指摘しておきたいと思います。
エネルギー政策は、安心・安全という問題はもとより、経済性、技術力、地球温暖化等の広汎な課題を、
多面的、総合的な観点で検討し、判断しなければなりません。
現実的に、電力インフラの整備は長期的な設備投資を必要とし、また技術力も一朝一夕に蓄積できるものではありません。
従ってエネルギー政策を決めても実際にそれが実現し、普及するには何十年という時間がかかります。
さらに忘れていけないのは、地球温暖化に関しては、数百年から数千年のスパンで考えなければいけない問題であるということです。
このように考えると、一国のエネルギー政策は、政権が変わるごとにがらっと変わっていいものではないことは明らかです。
エネルギー政策を政争の具とするのでなく、超党派的な議論をして国民のコンセンサスを形成することが必要だと強く感じています。
「東南アジアの物づくりビジネスに関して」
技術士(電気電子部門) 秋山 勇治
約20年前、日本の物づくり産業の海外移転が問題となり新聞紙上を賑わしたことがありました。
当時製造業が海外移転する事は日本産業の空洞化の懸念があり、何か悪いことであり、肩身の狭い思いをしたことを思い出します。
ところが最近では多くの製造業、特に部品加工、組立作業などの町工場型の産業は日本国内ではやっていけず、
海外移転こそが生き残る道であると、企業規模の大小を問わず、海外移転に切り替えています。
このような日本の製造業の変化をどう説明し理解すべきかを再度検討してみる事は有意義なことと考えます。
もしも20年前に日本の製造業、特に小物、電気製品、民生品等の中小企業主体の加工品を
当時日本製造業の空洞化防止の名のもとに近隣諸国に移転していなかったら、
今の日本経済はどうなっているか皆様想像してみていただきたいと思います。
さて現在の東南アジアのニーズの一つとして次のような状況があります。
私がアジアの発展途上国の政府の方々とお会いした時、
「現在世界で一番活力が有ると言われている東南アジア諸国の政府及び地方の首長の方々及び民間企業社長さんの方々が、
今日本に一番大きく期待しているのは、「その国の地方の産業用及び生活用の電力設備(インフラ)の支援」
だと実に明確に言い切っています。
「もしも日本の企業でこれら地方や僻地に対する電力インフラを支援していただけるなら、
その為に必要な土地や人間(人材)は我々(政府/自治体/経営者)が責任を持って無償で手配して提供します」と。
具体的な例ではそのような電力インフラを作る相模原市のあるベンチャー企業に東南アジアの政府高官、
企業家やアラブの王族の方々が見学に来たとも聞いています。
ここで言う電力インフラは日本で言うPPS(小規模な電気事業者)インフラに相当するものです。
私の集めた情報(タイ、ミヤンマー、フィリピン)では地方活性化の為のインフラの規模は
概略1ヶ所500~1,000kW程度で正に日本のPPSレベルのものです。
またその設備を運転維持管理する為の技術者は現地で手配するので日本からの支援は不要であるとのことです。
中小企業ベンチャーの皆様、上のようなニーズに是非チャレンジしていただきたいと考えます
「資源と開発」
技術士(化学部門) 渡辺 春夫
40年前、私が学生だった時、オイルショックがありました。
予測外の出来事でしたが原因は、石油消費国の不買兵糧攻めに耐える産油国の資産蓄積達成にありました。
産油国が勝利し、1バーレル2ドル程度の原油価格は、50ドルまで高騰しました。
当時、「成長の限界」(The Limits to Growth) と云う本が出て、
石油どころか、多数の金属資源、食料資源も早晩枯渇すると警告しました。
私は上記の理由で学生時代、炭素のガス化反応(水性ガス反応など、C+H2O=CO+H2)の触媒の研究をやりました。
石炭から褐炭に至る固形炭素質は世界に無尽蔵にあります。
これをガス化(CO,H2,CH4など)すれば、人造石油も化学品も容易に合成できます(実際、第二次大戦中のドイツや、
アパルトヘイトで禁輸の南アフリカで、石炭から人造石油が製造され使用されました)。
私も、ニッケル、コバルトから貴金属の白金族までⅧ族元素を、触媒として検討しました。
高価な白金族は活性があり、ニッケルも比較的良好な結果で、論文の被引用数の多い論文でした。
この研究は、政府の補助金を得て、以後10年以上続きました。後継者たちは、
オーストラリアの褐炭をニッケル触媒で100%低温ガス化できる画期的成果を挙げました。
しかし、その間に、石油価格は、すっかり落ち着いてしまい、この成果も、論文の査読者から、
「高価な?ニッケルを使うのは、工業的でなく実用性がない」と拒絶を受けるまでになってしまいました。
ところが、今や、「シェールオイル」、「シェールガス」で、世の中が変わろうとしています。
シェールオイル・ガスは、シェール層という石油・天然ガスが溶け込んでいる岩の地層を水平掘削し、
超高圧水と薬剤で岩を破砕し、採取する石油・天然ガスです。石油はあと30年で枯渇すると云われてきました。
ずっと変わらず30年でしたが。今や、100年以上は十分にあるようです。
結局、資源価格の高止りを背景にして、新たな物質を合成する技術よりも、
埋没している資源を効率的に採掘する技術開発の方が勝利したということです。またまた予測が外れました。
資源・エネルギーは、私自身、予測が外れっぱなしですが、英明なる国家のエリート達をしても
国家戦略が未だ定まらない難問であります。
これは、技術進歩、社会経済情勢、大規模災害など予測し難い要素に基づき、
予測しなければならないところに難しさがあるのだと思います。
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)

H24年度川崎市産業振興財団主催の人材育成セミナーは、先月終了しました。 本年度は、「電力」「省エネ」「商品開発」「技術管理」をテーマと して講演を行い盛況の内に終了致しました(右写真)。 H25年度も皆様のお役に立つセミナーを計画しておりますのでご期待下さい。 |
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| 技術士による技術窓口相談 (無料・要予約) |
13:30~16:30 | (例)公的支援、電気用品安全法、技術・経営に関すること |
| 緊急コンサルティング(無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援致します。最大3回可能です |
| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援 |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/
E-mail: t_koinuma@mtf.biglobe.ne.jp
NPO法人 かわさき技術士センターURL:http://www.n-kgc.or.jp/
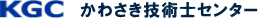
 技術支援ニュース
技術支援ニュース