- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
「企業の強み」
技術士(情報工学部門) 久田見 篤
中小企業の経営者の方にお会いすると、事業にかける想いや今後のビジョンについて熱心に語られて、
厳しい環境変化の中で多くの課題もありますが、それらに対する様々な取り組みについても熱意をもって話されます。
経営者のビジョンや熱意が事業経営にとって何よりの推進力であると感じます。
一方で、自社の製品や技術が他社と比べてどういう強みを持っており、お客様にどう評価されているかについてお伺いすると、
自信を持って回答していただける場合は少ないようです。他では得られない優れた製品やサービスを提供している会社でも、
自分達にとってはあたりまえの事だと捉えており、企業の特別な強みだとは認識していない場合もあるようです。
お客様から見た製品やサービスの良い点と経営者が考える自社の強みとの間にはギャップがあるように感じます。
お客様が製品を選択したり、繰り返し発注する背景には必ず理由があるはずです。
その理由を知ることができれば社内では気づかない企業の強みを再発見できる可能性が有ります。
お客様の本音を引き出すことは簡単ではありませんが、経営者の方がお客様の声にできるだけ多く耳を傾けることは
企業の強みを再確認するために重要であり、今後の事業経営のかじ取りに有益だと思います。
「国内製造業復活へ期待される“3Dプリンタ”」
技術士(機械部門) 白石 秀樹
政府は低迷する国内製造業の復活に向けて、6月の成長戦略に“3Dプリンタ”の分野へ、 2014年度から5年間で100億円程度の資金支援を行う方針を決めました。 3Dプリンタとは金型を用いた樹脂成型や工作機械による切削加工を行わなくても立体物が作れる造形ツールのことです。 次世代の日本の産業基盤となる可能性があります。 実は、日本では20年ほど前から同様な積層手法で紫外線やレーザー光を用いた立体の微細造形(光造形法)の研究が、 名古屋大学や一部のメーカーで行われてきました。 しかし、今注目されている3Dプリンタを用いれば、比較的自由に立体物が造形できます。 今や、欧米を中心に工業部品はもちろん医療分野、デザイン業界、建築業界などで応用が急速に拡大しています。 その拡大の背景には、大きく3つの理由があります。
- 装置の低価格化:ここ10年で10万円~数十万 円程度の比較的購入しやすい3Dプリンタが登場してきた。 代表的メーカとして米国Stratasys社など(国内にもメーカーあり)。
- SNS(ソーシャルネットワークサービス)の活用:商品メーカーのオリジナル3Dフリーソフトの提供や 安価な3次元CADデータのネット販売などのサービスがSNSを活用し展開してきた。
- 造形素材の多様化:3Dプリンタの主流はFDM方式(熱溶解積層法)で、細いABS線材をノズルから溶融状態で 射出しながら積層して立体を造形する。最近は業務用の上位機種ではPC(ポリカーボ)、PPSF(ポリフェニル・サルフォン)など 多様な素材が使用できるようになった。
では、今後の国内製造業の物づくりはどうなるでしょうか? 商品開発面では、光造形法に替えて3Dプリンタを活用すれば、試作品の製作が大幅に短縮化され、 開発期間がより短縮化されます。 さらに画期的なのは、3Dプリンタの性能が飛躍的に向上することにより素材(機能性プラスチック材など)の選択枝が増え、 例えば直接製品を製作できるので在庫が不要になったり、 個性的デザインのオンリーワン商品を簡単に受注・販売できます。 “3Dプリンタ”が製造業で汎用的に使われるようになれば、国内製造業復活は始まったと言えます。 この際中小企業の皆様にはこのイノベーションにぜひ具体的に取り組まれるようお薦め致します。
「低温の利用」
技術士(応用理学部門) 西田 啓一
低温と言えば何を思い浮かべるでしょうか。低温にもさまざまな範囲があります。
【代替フロンなどの利用による範囲】氷や雪の温度はよくご存じの0℃(1気圧)です。
氷を作るには冷凍機が使われますが、これは冷蔵庫などと同じ原理で代替フロンガス
(フロンガスは地球温暖化の原因となるため現在は使用禁止)を圧縮し、
このガスを小さい孔から膨張させると液体(沸点:-41℃)になります。
この液体が気体となるときの蒸発熱を利用して氷を作ったり、冷房をおこないます。
【ドライアイスや液体空気等利用の範囲】更に低い温度を得るにはドライアイスによります。
ドライアイスは炭酸ガスが凝固したもので、昇華(固体が気体になる)温度が-79℃です。
炭酸ガスを圧縮して、発生する熱を除去した後、小さい孔から膨張させると固体のドライアイスが得られます。
更に低い温度というと身近にはないかも知れません。液体メタン(沸点:-162℃)は都市ガス用として
海外から液体の状態で輸入されています。液体メタンが蒸発するときの気化熱で冷却した圧縮空気を
小さい孔から膨張させると液体空気が得られます。
この液体を蒸留装置で分離すると液体酸素(沸点:-183℃)と液体窒素(沸点:-196℃)が得られます。
酸素、窒素は液体の状態で貯蔵、運搬されて、医療用吸入ガスや冷凍食品の製造用としてなど幅広く利用されています。
【液体水素、液体ヘリウム等利用の範囲】液体水素(沸点:-253℃)や液体ヘリウム(沸点:-269℃)は
高圧に圧縮した水素ガスやヘリウムガスを液体窒素で冷却して小さい孔から膨張させると得られます。
液体水素は液体酸素とともにロケット推進剤として使用されます。
また、液体水素は自動車用の燃料電池に利用されようとしています。液体ヘリウムは
MRI(核磁気共鳴画像装置)の超電導用磁石を冷却するために利用されていますし、
磁気浮上列車用超電導磁石の冷却にも利用されようとしています。
【絶対零度に近い範囲】-273.15℃(絶対温度:0K[ケルビン])近辺でも応用が拡がっています。
このような極低温を利用する技術の分野は低温工学(Cryogenics)として注目されています。
低温工学を展開するために電気エネルギー→機械エネルギー→熱エネルギーの変換が利用されており、
その変換効率は重要なファクターですし、低温度の維持も重要な技術ポイントです。
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)
|
H24 年度川崎市産業振興財団主催の人材育成セミナーは終了しました。 |
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| 技術士による技術窓口相談 (無料・要予約) |
13:30~16:30 | (例)公的支援、電気用品安全法、技術・経営に関すること |
| 緊急コンサルティング(無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援致します。最大3回可能です |
| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援 |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/
E-mail: t_koinuma@mtf.biglobe.ne.jp
NPO法人 かわさき技術士センターURL:http://www.n-kgc.or.jp/
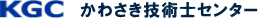
 技術支援ニュース
技術支援ニュース