- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
「中小企業の開発プロジェクトを支援して」
技術士(経営工学、総合技術監理部門) 服部昌幸
コロナ禍の少し前までの8年間、プロジェクトマネージャーとして中小企業の開発プロジェクトに関わりました。
各プロジェクト期間は半年から2年半で13テーマの新製品・新技術開発に取り組みました。中小企業の中には開発に手慣れた会社もあり、
販路まで確立した計画を着々と進め目標達成したプロジェクトもあります。
しかし、私が関わった中では製品開発はできたが販売先が見つからないことなどが多く、
他にも産学の連携が不調になったり、企業幹部の退職金のために資金不足が発生して開発を断念するなど、中小企業ならではの問題も発生しました。
成果を文字通り得られたのは少なかったと思います。一方、販売やコスト目標は未達でも開発し終えたことで自社技術のステップアップに満足している企業は多くいます。
プロジェクトには表面で評価される成果の他に、プロジェクトを組むことによる地域企業間の連携、
自分たちのブランドを持つことによる誇りの醸成、メンバーの開発技術力向上心の定着などの副次的な成果があるのは知られています。
「社長にまた、こんなもの開発しろと言われて・・・」とぼやく開発担当者の笑顔や「プロジェクトにしたらメンバーの結束がよくなった」と
素直に喜ぶ若いリーダーの明るい声が印象に残っています。
振り返ると、開発にチャレンジする経営者の姿勢は会社の元気の源であり、企業の維持発展の礎でもあることを知った8年間でした。
「重要な管理手段を見極めるマネジメント力」
技術士(経営工学部門) 和田吉正
欧米諸国との比較で遅れが指摘されていた食品衛生管理の方法が、今年6月に法制化・施行開始されたのをご存じでしょうか。3
年前の2018年6月に改正食品衛生法が公布され、これまでに小規模事業者でも実践できるようにと、
各業種団体と国により業種別に分かり易い手引書が作成されました。
衛生管理手法の名前はHACCP(ハサップ)と言います。HACCPとは、食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(Hazard:ハザード)を分析(Analysis:アナリシス)し
把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程の中で、
それらの危害要因を除去・低減するために特に重要(Critical:クリティカル)な管理(Control:コントロール)を
行うべき工程(Point:ポイント)を定めて製品の安全性を確保しようとする国際的な管理手法です。
従来、日本の食品工場では手洗い、マスク・帽子の着用、清掃・洗浄、防虫・防鼠などの一般衛生管理に重きが置かれてきました。
そのためか、日本人には「衛生管理+製品検査」で食品安全が保証できると早とちりする人が多いように感じます。
今後は国際競争力をつけるためにも、「重要な管理手段を明確化して管理の中心に据え、加えて一般衛生管理で製造環境を整え、
これら両輪で食品安全を保証する」というHACCP手法を普及していくことが急務です。
幸い2018年の改正食品衛生法公布以降はそれまで増加傾向にあった食中毒事故件数が減少に転じています。
大企業のみならず小規模事業者向けのHACCP研修も活発に開催されていることから、
遠くない将来にHACCP手法に基づく科学的な食品安全管理が我が国に根を下ろすことを期待しています。
話を転じて、我が国の新型コロナウイルス対策の特徴を振り返ってみます。日本では感染拡大初期からマスクの着用、手洗い励行、三密(密集、密接、密閉)回避など、
いわゆる一般衛生管理が対策の中心で、重要な管理手段であるワクチン接種は大幅に遅れました。
対照的に、欧米諸国はしっかりと重要な管理手段であるワクチン接種を優先しており、結果として早期経済復活を実現しています。
筆者が食品メーカー出身のため、食品安全に関するリスクマネジメント手法であるHACCPを取り上げましたが、
何らかの形で食品業界以外の読者の皆様にもお役に立てれば幸甚です。
「安全衛生への意識改革」
技術士(電気電子部門、総合技術監理) 鈴木安男
令和2年の労働災害の状況は、死亡者数802名(前年845名)、休業4日以上の死傷者数131,156名(前年125,611名)です。 死亡者数は過去最低にもかかわらず死傷者数は、ここ10年間は微増微減を繰り返しています。 死亡災害では、墜落・転落、交通事故、はさまれ・巻込まれで約60%、休業4日以上では 転倒、墜落・転落、動作の反動無理な動作、はさまれ・巻込まれで約65%を占めています。 このような状況の中で、都道府県労働局(労働基準監督署)は、例えば、労働災害発生件数が高い、 重大災害(一時に3人以上の死傷災害)発生職場、職場環境に問題があったり、 健康障害が懸念される事業場などを個別に指定(安全又は衛生管理特別指導事業場)して、 安全衛生改善計画などを作成させ、継続的な指導を通じ、課題解決により安全衛生水準の向上を図ることにしています。
1. 何をやればいいのか?取り組みは?:(1)労働局から指定された事業場は、まず安全衛生改善計画を作成します。 ①安全衛生診断により問題点の発掘を行い、テーマと内容を設定します。 ②労働災害の分析により問題点と課題を発掘し、テーマと内容を設定します。 ③行政の指導事項に対する課題解決のテーマと内容を設定します。
2. 安全衛生改善計画を基にして安全衛生改善実施計画書(1年間)を作成します。
3. 具体的なテーマ設定の例:①改善計画の基本方針、目標、②災害統計:度数率、強度率、①安全衛生管理体制、②職場施設等、③安全衛生教育など。
4. 年間を通じての労働基準監督署への報告:①四半期ごとに労働基準監督署へ報告、②安全衛生 改善実施計画書の実施状況(PDCA)の報告、③安全衛生委員会の議事録は必須、④年間途中で 労働基準監督署の現場査察がある。
5. 1年間で労働局が指定解除しなかったときは指定延長(継続)となります。
これらの問題解決には安全・衛生コンサルタントの診断を受け、改善計画作成などについて、支援を受けることができます。 安全・衛生コンサルタントは改善計画や改善計画書作成などについて年間を通じての安全衛生計画のテーマの課題解決を図り、 労働災害の大幅な減少と自主的な安全衛生管理体制の構築により、1年間で指定事業場から解除されることを目標に取り組みます。 安全又は衛生管理特別指導事業場は、安全衛生に対する事業場の大事な意識改革の期間とも言えます。
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)
 2021年度「KIIP公益法人川崎市産業振興財団」との共催(技術)セミナーを企画しています。
新型コロナウイルスの影響がまだまだ懸念されますが、9, 10, 11月の3回にわたり
各回16:00~18:00、90分間講義+30分間質疑応答の形態を予定しております。
2021年度「KIIP公益法人川崎市産業振興財団」との共催(技術)セミナーを企画しています。
新型コロナウイルスの影響がまだまだ懸念されますが、9, 10, 11月の3回にわたり
各回16:00~18:00、90分間講義+30分間質疑応答の形態を予定しております。
企画詳細は8月、振興財団より下記URLにて案内予定です。ご活用頂ければ幸いです。 https://www.kawasaki-net.ne.jp/ |
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| ワンデイ・コンサルティング(無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援します。最大3回可能です。 |
| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援。 |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/
NPO法人 かわさき技術士センター URL:http://www.n-kgc.or.jp/ E-mail: info@n-kgc.or.jp
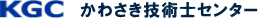
 技術支援ニュース
技術支援ニュース