- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
「「ソーラーシェアリング見学記」
技術士(総合技術監理部門)内藤 重信
去る10月15日(水)に、PV‐Net 神奈川地域交流会が主催する見学会に参加し、
千葉県匝瑳(そうさ)市と市原市に設置されている3か所のソーラーシェアリング設備を見学してきました。
ソーラーパネルを空き地に敷き並べたメガソーラーは設置例が多く、使用実績もたくさん報告されていますが、
このソーラーシェアリングは、畑作農地の上に農作業ができる高さ(ここでは2.7m)に、パイプ足場で骨組みを作り、
幅290mm、長さ1,580mm、厚み25mmのパネルを、パネル幅1に対し、2倍の空間を設けて敷き並べたもので、
畑作に必要な光合成も可能(遮光率 約30%)です。
風が吹き抜けるので、風力に対する構造体/基礎等の強度も比較的軽微なもので済む点も長所です。
メガソーラーのような雑草を刈り取る手間もなく、農業を営まれる方々にはお薦めの設置方法です。
発電を担うパネルも、太陽の動きに追随するように回転させることもできます。
これらのデータは今後、いろいろ報告されるでしょう。メンバーの方が掲載された下記のHPをご参照下さい。
http://blog.livedoor.jp/pvkanagawa/
「ガスの種類と分離・精製・用途・測定法」
技術士(応用理学部門) 西田 啓一
ガスといえばどのようなガスを思いうかべますか。都市ガスや屁のような臭いガスでしょうか。
最近では火山性ガスが話題になりましたが、身の周りでは空気が重要なガスです。
空気中に酸素が20.95%、窒素が78.08%含まれています。あまりご存じがないかと思いますが、
アルゴンが0.93%含まれています。これらのガスは空気を液化して沸点の差を利用して蒸留によって分離します。
最近はゼオライトや活性炭を使って分離するPSA法(圧力変動吸着法)が普及してきています。
酸素は溶接や吸入用ガス等として、窒素は食品の腐敗防止や半導体素子の製造過程での酸化防止ガスとして利用されています。
アルゴンは溶接用の不活性ガスとして不可欠です。
空気中にはこの他、微量ですが希ガスのヘリウム、ネオン、クリプトン、キセノンが含まれています。
忘れてはならないのが二酸化炭素(炭酸ガス)です。約0.039%(390ppm)含まれており、植物の成長に不可欠で、
地球温暖化の原因物質です。この他,大気汚染ガスである硫黄酸化物(SOX)や窒素酸化物(NOX)が含まれています。
熔接用のアセチレンや二酸化炭素、工業用水素、気球や人体の断層写真を撮るための装置の冷媒として重要なヘリウムは
酸素、窒素などとともに工業用ガスとして分類されます。
ご存じのように都市ガスは天然ガスのメタンを主成分としており、地域によりプロパン,ブタンが使用されます。
半導体素子を製造するために使用されるガスにはシランなど多くの種類のガスがあり、半導体ガスあるいは特殊ガスと称されています。
医療用ガスとしては吸入用酸素があり、その他、麻酔用の笑気ガス(N2O)があります。
大気汚染ガスとして硫黄酸化物、窒素酸化物やオゾン、一酸化炭素等があります。
また悪臭ガスとしてアンモニア、硫化水素、メチルメルカブタン等22物質が規定されています。
この他、自動車排ガス、毒ガス、放射性ガス、芳香ガス(香水)などがあり、それぞれの製造分野で生産され、
あるいは発生しており、有用に利用・活用される一方、公害をもたらしています。
これらのガスの濃度(純度、含有率)を測定する方法・技術は重要で、いろんな方法がありJISに規定されています。
ガスの濃度測定で絶対値を判定できる絶対値法はほとんどなく、標準ガスとの対比で求めることが多く、
標準ガスの製造、精度管理も重要技術になります。
製造法、利用法、分析法(測定法)や公害ガス等の発生原因や除去法については、
各分野の技術者が真剣に取り組んでいる課題になります。
「TPM手法を活用したISO9001による業務改善」
技術士(経営工学) 佐藤 幸雄
ISO9001は品質優良企業のパスポートと言われ、ISO9001には企業運営に必要な事項が「要求事項」として規定されています。
要求事項は、マネジメントシステムとして具備せねばならない世界共通の要求内容です。
しかし、中小企業にとっては、要求事項を満足させるためには改善せねばならない事項が多く存在します。
ISO9001の要求事項で「・・・しなければならない」と規定してあるが、「誰がどのようにすべきか」は各企業が決めねばなりません。
そして、それが確実に実行されるように業務を改善して標準化せねばなりません。
この改善と標準化を効率よく実施し、定着させることが大変で、ISO9001の認証を取得したが、
要求事項の内容を業務に反映できないでいる企業が多く存在します。
このたび、ISO9001の認証の取得を支援した中小企業に対し、その改善成果を業務に発揮させるべく、
TPMの手法を業務に取入れ、改善の成果を上げたので、その事例を紹介します。
TPMはTotal Productive Maintenance「全員参加の設備保全活動」の略称で、日本メンテナンス協会が提唱し、
優秀な会社に賞を与えるシステムです。中小企業向けで第一段階になる賞は「TPMチャレンジ賞」です。
この受賞活動はISO9001を活用した改善活動の実行に大変役に立ちます。例を挙げれば、ISO9001の要求事項に、
「製品実現の全過程において適切な手段で製品を識別しなければならない」、「必要に応じて作業手順が利用できる」、
「適切な設備を使用している」の規定があります。
これに対応するものとして、TPMの自主保全活動では次のステップの実行が要求されます。
①第1ステップ:初期清掃、②第2ステップ:清掃困難箇所対策、③第3ステップ:仮基準書の作成。
それぞれのステップに対し合格のための審査基準があり、確実に実施せねばならない仕組みとなっています。
私が改善の支援を行った従業員30名の企業は、ISO9001を活用した企業体質の改善を実行するためにTPMチャレンジ賞を受賞しました。
この受賞活動により、現場は活性化して5Sが徹底し、企業の運営体制が見違えるほど改善されました。
顧客からは大きな賞賛をいただき、受注増加に貢献しました。
また、先日、実施されたISO9001の定期審査では、審査員の質問に対し、
TPMでの実施内容を説明することで完璧な回答となり、
審査員からお褒めの言葉をいただきました。
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)
| メニュー | 日 時 | 内 容 |
|
平成26年度 技術セミナー (14:00〜16:30) 川崎市産業振興 会館 9 階 第1研修室 |
2014年 12月10日(水) |
「これで納得! 電源回路にコンデンサが必要な理由」 技術士 佐野芳昭 「電子機器の信頼性設計とFMEA解析手法」 技術士 増田久喜 | 2015年 1月14日(水) |
「労働安全リスクアセスメントの課題と対策」 技術士 鈴木安男 「ISO9001 とTPM の融合改善で現場を活性化し、安定受注体制の構築」 技術士 佐藤幸雄 |
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| 技術士による技術窓口相談 (無料・要予約) |
13:30~16:30 | (例)公的支援、電気用品安全法、技術・経営に関すること |
| 緊急コンサルティング(無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援致します。最大3回可能です |
| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援 |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/
NPO法人 かわさき技術士センター URL:http://www.n-kgc.or.jp/ E-mail: info@n-kgc.or.jp
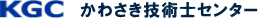
 技術支援ニュース
技術支援ニュース