- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
コラム 「日本技術士会の継続研鑽(CPD)」 技術士(生物工学) 木幡 守
すべての企業にとって人材は「財産」です。従って、企業はそれぞれ独自の人材育成カリキュラムを
計画・実践しているであろう。それらの中で、現場の実務が人材育成にとって重要な教育・研修の場で
もあることは論を待たない。しかしながら、企業内での人材育成には限界があるし、さらに視野を広げ
るためにも外部の力も活用しなくてはならない。今やいろいろな団体が各種の講演会やセミナーを企画
し実施しています。ここで、日本技術士会の講演会――CPD 中央講座――を紹介したい。
技術士は、技術士法において「自己の資質向上のための継続研鑽(CPD)」が責務となっています。
CPD の目的は、① 技術者倫理の徹底、② 科学技術の進歩への関与、③ 社会環境への対応、④ 技術者としての判断力の向上、
新しい知識の取得と自己啓発、などです。
日本技術士会では 19 部会やプロジェクトチームごとに様々の講演会・セミナーや見学会を実施していますが、
そのほかに、技術士共通の講演会として、生涯教育推進実行委員会が毎月、CPD 中央講座やミニ講座の名前で講演会を
企画・実施しています。CPD 中央講座等の案内は月刊「技術士」やホームページ
(URL: http://www.engineer.or.jp/)で見ることができ、
技術士会員でなくても参加することができます。
そこでは新しい人脈の開拓にもつながります。皆様も参加してみてはいかがでしょうか。
気になる用語 「持続可能な社会の発展」 技術士(化学部門) 湖上 国雄
最近、地球温暖化問題、オゾン層破壊問題、黄砂問題、食糧問題等のグローバルな地球環境問題を解 決するために、 「持続可能な社会の発展」 :Sustainable Society Development という環境と経済の持 続的両立を求める概念が強まってきました。現在の状態のままでは、エネルギー・物質の大量消費・廃 棄による資源の枯渇と環境の汚染が急速に進み、遠くない将来に地球の許容限度を超えて、地球そして 人間文明が、破局に至ってしまうという恐れがあります。エネルギーに関しては、1 次エネルギ-の確 保とエネルギーの節約、 エネルギー変換・利用効率の向上が求められています。 資源(物質)については、 資源枯渇の回避と廃棄物対策の観点から、効率的な資源利用、有効な廃棄物再利用が必要です。また、 注) 地球サミットのアジェンダ 21 に沿った化学物質のリスク評価・管理の強化と共にその安全に関わる 科学の推進”環境に優しいもの作りの化学”が求められています。以上のべてきたように、「持続可能 な社会の発展」とは環境の保全と経済社会の向上・発展を達成するものです。 注)1992 年リオデジャネ イロで開催の国連環境開発会議で採択された 21 世紀に向けて持続可能な開発を実現するための具体的行動計画
連載解説 「リスクアセスメント」(第2回) 技術士(電気電子 総合技術監理部門) 鈴木安男
リスクアセスメントは平成 18 年 4 月に事業者の努力義務として労働安全衛生法に規定されました。
このリスクアセスメントをスムーズに実施できるように「指針」も公表されました。また、安全配慮義
務の履行には危険予知(予見)の義務と結果回避の義務(労働災害防止措置)が必要でこれをクリアー
するためにもリスクアセスメントは有効な手段です。
リスクアセスメントは、 安全衛生計画作成時、 管理者・スタッフ・監督者・作業者のグループで実施、
作業対象の特定、作業を思い起こしながら作業手順書を基に、大きなリスク向け、主に設備面の対策の
ための手法です。よく、危険予知(KY)との違いは何かという話題が出ます。危険予知は作業の都度、
作業者・監督者、主に作業を確認しながら即断即決、小さなリスク向け、主に行動面の対策のための手法です。
リスクアセスメントの大まかな手順は、 「危険性又は有害性」の特定(具体的な危険源の発掘)→リ
スクの見積り(ケガの程度は、発生可能性という観点からリスクを見積もります)→リスク低減のため
の優先度の設定(直ちに解決すべき重大なリスクはある、速やかに低減措置を講ずる必要がある、必要
に応じてリスク低減措置を実施すべきリスクがある) 、リスク低減措置の検討(その仕事をなくせない
か、安全装置等を設置できないか、教育訓練等の管理的対策はできないか、保護具の使用はできないか
等)→リスク低減措置の実施(具体的な低減措置を実施します)→記録という流れになります。導入時
は多?とまどうことがあるかもしれませんが、慣れてくるとスムーズに展開されます。できれば導入時
は専門家かわさき技術士クラブ等のアドバイスを受けると考え方、具体的な現地での実施方法、適切な
評価方法、的確な指導等を受けることによって安心して定着させ、継続的な改善が可能となります。
これらリスクアセスメントが定着することによって、次の段階である労働安全衛生マネジメントシス
テム(OSHMS)への展開が容易になります。つまり、経営の中に OSHMS を組み込むことで経営と一
体となって労働災害をなくし(減?させ)快適な職場形成に寄与するものと考えます。
いずれにせよまずは「やってみましょう」 。実際に経験することによって危険性又は有害性の「感性」
が高められ、いろんなことに「気づく」はずです。
私たちかわさき技術士クラブは中小企業のみなさんへ懇切丁寧に支援し、ご満足をいただけるものと
考えております。
お役立ち最新情報
[支援事業]
| 技術士による 技術窓口相談(無料) |
毎週金曜日 13:30~16:30 |
7月4日、7月11日、7月18日、7月25日、8月1日、8月8日、8月15日、8月22日、8月29日 |
| ワンデイコンサルティング (無料) |
随 時 | ・派遣は、川崎市内の中小企業で1日(2時間)程度 ・派遣回数は、同一年度で1企業3回 |
| 専門家派遣(有料:半日 12,000円、1日 24,000円) | 随 時 | ・半日(3時間程度)の場合は、20回まで。12,000円/半日 ・全日(6時間程度)の場合は、10回まで。24,000円/日 |
中小企業サポートセンターは、中小企業を応援する総合的な支援機関です。
主な支援事業は次のとおりです。どうぞご利用ください。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
【問い合わせ先】〒212-0013 川崎市幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館6階
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp
E-mail: f-mutoh@df6.so-net.ne.jp 「かわさき技術士クラブのHP」: http://gijyutusi.sblo.jp/
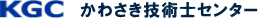
 技術支援ニュース
技術支援ニュース