- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
ご挨拶 川崎市産業振興財団理事長 曽禰 純一郎
かわさき技術士クラブの皆様には、2002年の発足以来、川崎市産業振興財団がおこなっている
窓口相談、専門家派遣、人材育成セミナーなど川崎市の中小企業サポートセンターとしての事業に
多大なご支援・ご協力をいただいていることに対しまして厚くお礼申し上げます。
リーマンショックから2年経過し、大企業を中心に徐々に「回復」が進んでいると言われていますが、
市内中小企業を取り巻く環境は、依然厳しい状況にあると思います。
こうした中で、私達財団としても、さまざまな経営課題を抱えている中小企業の方々のニーズに適った、
真に役に立つサービスをどのように提供していけるのか、より効果的な事業のあり方はどのようにあるべきか、
など中小企業サポートセンター事業のあり方について、必要な見直しを行うことが不可欠であると考えています。
かわさき技術士クラブは、幅広い分野にわたって各々の技術士の方々がお持ちになっている各自の専門性を活かして、
中小企業の抱えている課題に応じた「技術・経営」支援を行う専門家集団でもあります。
今後とも、現場に精通された専門的な視点に立った積極的なご提言をいただきたいと思います。
産業のまち・かわさきをもっと元気にするためには、市内の中小企業の活性化が不可欠です。
皆様方のより一層のご支援・ご協力をお願いします。
安全管理のはなし 技術士(総合技術監理部門、電気電子部門) 鈴木 安男
平成21年全産業の死傷者数は、約106,000人(死亡者数は1,075人)です。
その内の製造業の死傷災害数は、約23,000人(死亡者数は186人)で全産業の約2割です。
また、全産業の死傷者数80%は100人未満の事業規模で発生し、50歳以上が約4割を占めています。
そもそも安全管理とは、事業運営に伴う災害の絶滅(ゼロ災)を目指して経営者の行う合理的、組織的な施策であり、
目的は「ゼロ災」です。安全管理項目の主なものは、以下の通りです。
(1)安全管理体制の整備 労働災害は生産現場で発生するものであり、安全管理が生産ラインと常に一体化されることが重要です。
経営トップは、安全管理には最高の責任(方針、目標、計画)があります。
決して担当者任せにしないことです。また、各管理・監督者の責任と権限を明確にし、
相互のコミュニケーションを良くすることです。安全委員会についてもこれを積極的に活用し、
常に現場の意見を施策に反映することがポイントです。
(2)職場の施設・設備等の把握 職場の問題点を調査・把握し具体的な改善計画を立てることです。
そのためには、リスクアセスメント(危険性の事前評価)を実施し、その結果を踏まえて、対策を立てることが重要です。
問題点の調査・把握項目の具体例は、過去の災害事例、安全点検、工場内レイアウト、作業工程、施設・機械設備、建物、敷地などです。
改善計画は、効果的で無理のない実行可能なものであることがポイントです。
(3)安全教育の充実 多くの災害は、同種・類似災害の繰り返しなので、
この点を十分に考慮し、計画的な安全教育を実施します。
経営トップは、安全教育の実施状況の確認や確認後のフォローアップが必要です。
安全教育の具体例は、作業手順の整備、作業方法の改善や新規採用者、作業内容変更労働者、
危険有害業務従事者の教育などです。
(4)職場安全活動の推進 「ケガと弁当は自分持ち」といわれるように、
安全は他から与えられるものではありません。活動の具体例は、安全提案制度(報奨金も含む)、
安全当番制度(安全パトロールや朝礼スピーチ)、
危険予知活動(KYK)、ツールボックスミーテイング(TBM)、朝礼による安全指示などです。
これらの安全管理は、労働災害防止と快適職場のために、総合的な改善措置を実施することが肝要です。
かわさき技術士クラブは親身になってご支援します。
MOT 第12回 レビュー MOT体系 技術士(経営工学部門) 前田 知久
これまでMOTについて、11回のコラムで幅広い種々のテーマでMOTの要点が論じられてきました。
読者の中には、それぞれがどういう繋がりがあるのか疑問を持たれた方もおられるのではないかと思います。
シリーズが一巡するこの第12回ではMOTの体系をレビューし考え方を整理します。
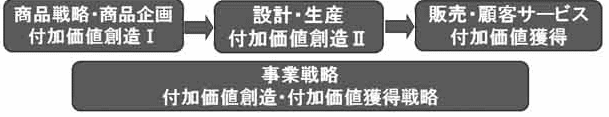 MOTの狙いは、製造業において技術・商品に関する事業戦略的マネジメントにより、「高い付加価値」を創造し、
これを販売・サービス提供することにより「高い対価」を獲得することにあります(右図参照)。
MOTの狙いは、製造業において技術・商品に関する事業戦略的マネジメントにより、「高い付加価値」を創造し、
これを販売・サービス提供することにより「高い対価」を獲得することにあります(右図参照)。
付加価値創造Ⅰ:付加価値創造では競争力のある商品戦略・商品企画が最大のポイントです。
ここで重要なのは、独自の技術など自社の強みを十分認識し商品構想を作り、
これが市場に受け入れられるよう種々マーケティング手法などを通して商品戦略・商品企画を練り上げることです。
付加価値創造Ⅱ:付加価値は商品の設計、製造などの実施プロセスでも創造できます。
設計段階での企画を凌駕する商品力の付与、カイゼン活動などによる製造コストの削減などがこれにあたります。
付加価値獲得:創造した付加価値は商品を販売することにより、はじめて対価を獲得できます。
ネットマーケティングなど新販売法なども取り入れた販促活動の強化も重要です。
顧客ニーズに応えるアフターサービスなども重要な収益源となります。
事業戦略:商品は一発勝負ではなく継続しなければ企業は成り立ちません。
事業継続のためには上記活動をサポートする技術開発の重点化、商品ラインアップ構成など中長期を見据えた戦略が必要です。
MOTシリーズで取り上げた各テーマは上記4つのどれかのカテゴリーに当てはまります。
レビューしそれぞれがどの位置付けなのかをチェックすることはMOT体系理解の助けになります。
MOT第3回と7回の「新製品開発」は付加価値創造Ⅰ、第9回の「ISO9001活用」は付加価値創造Ⅱ、
第5回の「知的資産経営」、第6回の「リスクマネジメント」は事業戦略の内容と言えるでしょう。
第4回「マーケティング」は付加価値創造を主体に販売・サービス、事業戦略にも言及しています。
お役立ち最新情報
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| 技術士による技術窓口相談 (無料・要予約) |
13:30~16:30 | (例)公的支援、電気用品安全法、技術・経営に関すること |
| 緊急コンサルティング(無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援致します。最大3回可能です |
| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援 |
| この度の東日本大震災で被災された皆様及び関係者の皆様に心よりお見舞い申し上げます。 一刻も早い復旧復興をお祈り申し上げます。 (2011.3.16 かわさき技術士クラブ) |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp
E-mail: t_koinuma@mtf.biglobe.ne.jp
かわさき技術士クラブURL:http://gijyutusi-club.sakura.ne.jp/
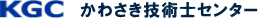
 技術支援ニュース
技術支援ニュース