- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
コラム 「省エネルギーと地球温暖化対策」 技術士(電気電子部門) 岡野 庄太郎
地球温暖化対策に関する京都議定書が発効され、わが国においては温室効果ガス削減努力を継続中で
すが、昨年度の実績は+8%となって合計-14%の削減を迫られています。このうち、民生用システムのオ
フィスビル、家庭用設備による影響は増加の一途を辿っています。勿論、運輸関連は基本ベースが大き
く、石油高騰の影響もあって、バイオエタノールの国際動向は、食糧問題にも発展しております。
このような状況下にあって、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の作業部会で過去、未来の予測
を含めてこの 4~5 月にかけて「温暖化が世界に及ぼす影響を予測」と「温暖化の影響の緩和策につい
て 」 その対策・状況等によるシナリオをまとめています。下記のURLを参照してください。
http://www.data.kishou.go.jp/climate/cpdinfo/ipcc/ar4/ipcc_ar4_wg1_spm_Jpn_rev.pdf
この対策として、ドイツサミットにおいて日本が指導力を発揮し、EU、カナダ、日本の 3 ケ国が 2050
年までに温室効果ガスの半減に関する取組みを提示してほぼ合意する内容が発表されています。さまざ
まな対策の中で「省エネルギー技術」は日本が最も優れているものと思われますが、あまり気付いてい
ない事項として、冷房方式の代表であるヒートポンプを「給湯」に使用することがあります。家庭用で
はエコキュートがこれに当たるのですが、エネルギー消費効率(COP)も 4.5~10 以上の機器も開発さ
れ、給湯の必要な事業所、産業用にも適用を考える時代となりました。
気になる用語 「データマイニング」 技術士(農業部門) 奥秋 明
マイニングは鉱山で行われていた選鉱(Mining)が語源で、膨大なデータの中から隠れた有用な情報
を取出す技術の呼称である。POS データ解析システムがその代表例で、リアルタイムでの在庫や販売予
測など不可欠の武器となっている。古典的成果で「紙オムツを買う消費者は同時にビールを買う」という
併売現象があり、消費者の併売行動の発見等売上げ増大に繋がる相関の発見も期待されている分野です。
現在、消費者行動調査やアンケート調査等のデータ解析から消費者ニーズを織込んだ「消費者満足の
商品創り」が提唱されているが、これも「データマイニング」の事例そのものである。採取データの解析
方法は多彩であり多くの解析用ソフトも発売されていますが、表計算ソフトとして普及している「エク
セル」でも基本的な多変量解析機能を備えているので、採取するデータの内容と、解析方法を選べば開
発担当者が必要とする目的に充分使用できます。関連する書籍もパソコンショップ等で扱っています。
採取したデータから宝ものが見つかる可能性があります。気楽に挑戦されたらいかがでしょうか?
連載解説 「環境経営」 (第2回) 技術士(機械部門) 遠藤 民夫
前号で環境経営とは「環境保全を進展させると同時に利益創出を実現させてゆく経営」と定義し、私
見を述べました。今回は、中小企業の環境経営の実践について、まず法令順守から述べます。
1.法令順守
法令を順守することが環境保全活動の第 1 歩となります。まず大気汚染、水質汚濁、エネルギー消費、
騒音などについて自社の生産活動がどのような環境影響を与えているか調査します。影響を与えている
活動があれば、それに関連した法規制を調べ、該当する法令があれば順守する必要があります。何が該
当するか分からない時は市役所、又は我々技術士に相談してください。万一、法規制値オーバや届出漏
れ等があれば早急な対応が必要です。法令順守に問題なければ、環境影響を継続的に緩和すべく、改善
目標を定め自主的改善活動を行ないます。法令順守は企業の社会的責任の重要な要素でもあります。
2.自社の本業における環境保全活動
自社の本業(機械加工業であれば、機械加工そのもの)の改善活動が、環境保全活動となり、経費節
減(経済効果)に繋がる仕組みを作ります。環境先進企業はこれらの活動で確実に成果を上げています。
- まず製造現場の基本となる 5S(整理、整頓、清掃、清潔、躾)が環境保全にとっても有効です。そ の理由は整理、整頓が出来ていないと、1作業効率が上がらず工場操業時間が増加しエネルギー等の 消費が増える。2部品が見あたらず、再手配すれば、資源の無駄遣いとなる。等によります。整理、 整頓が出来ていない企業は、環境保全活動も出来ないと言って過言ではありません。
- 不良品が発生すれば廃棄物が生じ資源の浪費となり、さらに再製作のためのエネルギーが必要となり となります。品質管理を徹底し不良率を低減すれば環境保全上も大きな意味を持つこととなります。 これら以外にも多様な改善活動が考えられます。当たりまえの事と思うかもしれませんが、これらの 活動(成果)を数値化し月次管理し、継続的改善活動に繋げて行く仕組みを作ることが重要です。
環境経営とはこのように地道な活動の積み上げです。経営者が環境保全の重要性を認識し、その方針 を確立し、従業員への周知、環境教育する事から始めます。改善目標を明確に定め環境保全活動を進め ます。そして、自社の環境活動、実績を公開しましょう。従業員の活性化にもつながります。
お役立ち最新情報
[支援事業]
| 技術士による 技術窓口相談(無料) |
毎週金曜日 13:30~16:30 |
7月6日、7月13日、7月20日、7月27日、7月6日 8月3日、8月10日、8月17日、8月24日、8月31日 |
| 出張相談(無料)【新設】 | 随 時 | ・中小企業や起業家で構成される「団体や事務局」に専門家が出向いて経営課題についてアドバイスします |
| ワンデイ・コンサルティング (無料) |
随 時 | ・派遣は、川崎市内の中小企業で1日(2時間)程度 ・派遣回数は、同一年度で1企業1回 |
| 専門家派遣(有料:半日 12,000円、1日 24,000円) | 随 時 | ・半日(3時間程度)の場合は、20回まで。12,000円/半日 ・全日(6時間程度)の場合は、10回まで。24,000円/日 |
中小企業サポートセンターは、中小企業を応援する総合的な支援機関です。
主な支援事業は次のとおりです。どうぞご利用ください。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★「かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
【問い合わせ先】〒212-0013 川崎市幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館6階
E-mail: f-mutoh@df6.so-net.ne.jp
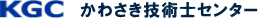
 技術支援ニュース
技術支援ニュース