- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
コラム 「アウトソーシング」で思うこと 技術士(機械部門) 内藤 重信
「アウトソーシング」という言葉は、「業務の外部委託」と訳され、自社で行うべき業務の一部(又は全体)を、
他社に委託することで、大雑把にいうと所謂「外注」に当たります。ISO9001 規格では
発注者側に立った発注仕様項目が規格化されています。
一方、受注する側、中でも下請け・孫請け等の言葉で呼ばれる側は、発注者の資本系列下にある場合が多く、
そうでなくても一般的には低コスト・短納期で製品を納入するよう要請され泣かされています。
しかし、こうした中にあっても自社の得意とする技術を活かし、それを磨き継承し、販路を拡大させて成長している会社もあります。
”社長の才覚”だと言ってしまえば身も蓋もない話になりますが、要は、自社の特徴・売り物
(要素技術やサービス業でのノウハウなど)は何かを自覚し、その応用分野(過去・現在・将来を展望して)・地球規模での時代の流れを考えて、
これで行くのか/他の技術と融合又は代替させるのか等の見通しをたてつつ、
原材料調達から販路先・アフターサービスまでの業務を、資金と人材を効率的・計画的に活用することだと言えます。
しかし「言うは易き」で、日頃の業務に忙殺される社長さん方にとっては大変です。
人脈を拡げインターネットを活用し情報を採りいれると共に、唯我独尊に走らず他人の意見に耳を傾ける度量・冷静さと従業員を引張ってゆく情熱、
更には失敗しても挫けない粘りと再挑戦するエネルギーも必要です。
振返って、そうした企業を支援する我々コンサルタントの責務は重大で、
見識を広め心身ともに健全・健康な状態を維持することの重要さを再認識した次第です。
気になる用語 「ヒヤリ・ハット」 技術士(電気電子部門) 鈴木 安男
ヒヤリ・ハットは、職場のみならず日常の生活においても雨や雪の日に道路で滑った等、災害にはならず
災害一歩手前で済んだ「ヒヤリ」としたり「ハット」したことは誰しも少なからず実際に経験していま
す。これがヒヤリ・ハットです。
過去にアメリカのハインリッヒは、死亡・重傷 1 件に対し、同種の 29 件の軽傷の災害があり、その陰に
は 300 件のヒヤリ・ハットがあることを研究・発表しました。つまり、300 件のヒヤリ・ハットをなく
さなければ、死亡・重傷や軽傷はなくせないということを意味しています。
近年、職場の労働災害は年々減少の傾向を辿り、喜ばしいことの一方、危機感が薄れ、安全管理・活動が
形骸化しています。このように、職場の労働災害は減っているけれども、裏に潜んでいる危険(潜在的な
危険有害要因)はいっぱいあるため、このヒヤリ・ハットの貴重な体験の情報を安全管理に取り込み、組
織的に活用し、労働災害を予防しようという動きが活発になっています。
連載解説 サポーティングインダストリー (第2回) 技術士(機械部門) 武藤 文男
前回(第1回)では中小企業への具体的支援策である「新産業創造戦略 2005」に提案された 1.燃料
電池、ロボット等の新産業 7 分野と 2.新材料・基盤技術(サポ-テイングインダストリ-)についての
施策重点化について概要を記しました。今回は 3.横断的な重要政策として(1)人材の育成・強化と(2)
知的資産重視「経営」の促進及び本年 8 月実施した事業予算について解説します。
3.横断的政策の展開
(1)人材、技術等の蓄積・進化
~競争力を支える人材の育成・活用。出口を見据えた効果的な研究開発の促進等~
・ 高専等を活用した人材の育成支援。大企業 OB 活用による製造中核人材育成事業。
・ 技術戦略マップを活用した効果的な研究開発。
・ 経営資源の潜在力を引き出すIT活用推進。
・ 人材・研究開発・IT の投資促進税制。
(2)知的資産重視「経営」の促進
~知的資産重視の経営を行い、それが市場からも適正に評価され、企業価値を高めるメカニズムの構築~
(注)知的資産とは人材や技術など財務諸表に現れない「見えざる資産」である。
・ 中小企業知的資産の評価・管理・活用・開示のための手法づくり。
・ コア人材・コア技術の適正管理(「営業秘密管理指針」の改定等)など。
4.平成 18 年度「戦略的基盤技術高度化支援事業」予算額:64 億円
(1) 事業の目的:我が国経済を牽引していく重要産業分野の競争力を支える重要基盤技術
(鋳造、鍛造、切削、メッキ等)の高度化に向けた研究開発を支援する。
(2) 川下ユ-ザ-(大手企業)と川上中小企業との共同研究体で実施。
平成 19 年度事業についてはこれから発表される予定。
他に特許料の特例、中小企業金融金庫の低利融資、知財駆け込み寺の整備・拡充等施策展開
中小企業庁ホ-ムペ-ジ(http://www.chusho.meti.go.jp)
以下次号に続く。
お役立ち最新情報
[オーディション]
| メニュー | 日 時 | 内 容 |
| かわさき起業家オーディション ビジネス・アイディア市場 |
最終選考会 2月10日(土) |
かわさき技術士クラブは起業家、中小企業者の皆様のご応募を全面的に支援いたします。 応募要領は、http://www.kawasaki-net.ne.jp/ |
[技術士によるセミナー]
| 平成19年度セミナー (9階 第2研修室)(無料) |
2月 7日(水) 18:00~20:00 |
ISOの活用法 技術士(経営工学) 佐藤 幸雄 |
[支援事業]
| 技術士による技術窓口相談 | 毎週金曜日 13:30~16:30 |
1月5日、1月12日、1月19日、1月26日 2月2日、2月9日、2月16日、2月23日、 |
| ワンデイコンサルティング (無料) |
随 時 | ・派遣は、川崎市内の中小企業で1日(2時間)程度 ・派遣回数は、同一年度で1企業1回 |
| 専門家派遣(有料:半日 8,000円、1日 16,000円) | 随 時 | 派遣回数は、川崎市内の中小企業で1企業あたり全日(6時間)の場合 10回、半日(3時間)の場合は20回まで |
中小企業サポートセンターは、中小企業を応援する総合的な支援機関です。
主な支援事業は次のとおりです。どうぞご利用ください。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★「かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
【問い合わせ先】〒212-0013 川崎市幸区堀川町 66-20 川崎市産業振興会館6階
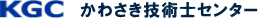
 技術支援ニュース
技術支援ニュース