- 全号目次
- 第100号(2025/03)
- 第99号(2024/12)
- 第98号(2024/09)
- 第97号(2024/07)
- 第96号(2024/03)
- 第95号(2023/12)
- 第94号(2023/09)
- 第93号(2023/07)
- 第92号(2023/03)
- 第91号(2022/12)
- 第90号(2022/09)
- 第89号(2022/07)
- 第88号(2022/03)
- 第87号(2021/12)
- 第86号(2021/09)
- 第85号(2021/06)
- 第84号(2021/03)
- 第83号(2020/12)
- 第82号(2020/09)
- 第81号(2020/06)
- 第80号(2020/03)
- 第79号(2019/12)
- 第78号(2019/09)
- 第77号(2019/06)
- 第76号(2019/04)
- 第75号(2019/02)
- 第74号(2018/12)
- 第73号(2018/10)
- 第72号(2018/08)
- 第71号(2018/06)
- 第70号(2018/04)
- 第69号(2018/02)
- 第68号(2017/12)
- 第67号(2017/10)
- 第66号(2017/08)
- 第65号(2017/06)
- 第64号(2017/04)
- 第63号(2017/02)
- 第62号(2016/12)
- 第61号(2016/10)
- 第60号(2016/08)
- 第59号(2016/06)
- 第58号(2016/04)
- 第57号(2016/02)
- 第56号(2015/12)
- 第55号(2015/10)
- 第54号(2015/08)
- 第53号(2015/06)
- 第52号(2015/04)
- 第51号(2015/02)
- 第50号(2014/12)
- 第49号(2014/10)
- 第48号(2014/08)
- 第47号(2014/06)
- 第46号(2014/04)
- 第45号(2014/02)
- 第44号(2013/12)
- 第43号(2013/10)
- 第42号(2013/08)
- 第41号(2013/06)
- 第40号(2013/04)
- 第39号(2013/02)
- 第38号(2012/12)
- 第37号(2012/10)
- 第36号(2012/08)
- 第35号(2012/06)
- 第34号(2012/04)
- 第33号(2012/02)
- 第32号(2011/12)
- 第31号(2011/10)
- 第30号(2011/08)
- 第29号(2011/06)
- 第28号(2011/04)
- 第27号(2011/02)
- 第26号(2010/12)
- 第25号(2010/10)
- 第24号(2010/08)
- 第23号(2010/06)
- 第22号(2010/04)
- 第21号(2010/02)
- 第20号(2009/12)
- 第19号(2009/10)
- 第18号(2009/08)
- 第17号(2009/06)
- 第16号(2009/03)
- 第15号(2009/01)
- 第14号(2008/11)
- 第13号(2008/09)
- 第12号(2008/07)
- 第11号(2008/05)
- 第10号(2008/03)
- 第 9号(2008/01)
- 第 8号(2007/11)
- 第 7号(2007/09)
- 第 6号(2007/07)
- 第 5号(2007/05)
- 第 4号(2007/03)
- 第 3号(2007/01)
- 第 2号(2006/11)
- 第 1号(2006/09)
「人工知能について思うこと」
技術士(機械部門) 磯村 正義
グーグルの人工知能「アルファ碁」が韓国の名人に勝ったことが大きな話題になっています。
人工知能が騒がれたのは今回が初めてではありませんが、最近のコンピュータの発達、ビッグデータ、
またディープラーニングと呼ばれる新しい手法の発展によって、最近の人工知能の発達は目を見張るものがあります。
これらのニュースを見て、人工知能がやがて人間を超えるのではないか、あるいは人工知能が人間の仕事を奪うのではないか、
というような論調がまことしとやかに囁かれたりもします。
しかし科学技術の発展に伴い、古くはラッダイト運動(19世紀にイギリスの織物工業地帯に起こった機械破壊運動)や、
比較的最近では産業用ロボットの普及の際にも似たようなことが言われたことがありましたが、結果的にはそうはならず、
人間がより人間らしい生き方をすることに貢献してきたと思います。
中小企業の経営において、将来人工知能を活用する時代が来るかもしれませんが、経営にとって代わることはあり得ないと思います。
企業活動はルールの決まったゲームではなく、創造性を競う場であると考えるからです。
人工知能の発展は、私たちがより知的な、創造的な生き方をするためのチャンスを与えてくれるものだと、積極的に評価したいものです。
「農業法人における総合的マネジメントの必要性」
技術士(機械部門) 白石 秀樹
TPP法案(環太平洋経済連携協定)の成立により国際的な市場開放が進むことで日本の農業の国際競争力が評価されようとしています。
そのような中で、農業経営の法人化、それも大規模化により生産性の向上を図り顧客のニーズ多様化に対応した商品をタイムリーに市場に提供できる法人が市場での競争力を得ます。
改正農地法が2009年12月に施行されて以来、一般法人の農業参入が大幅に増加しており、施行前に比べて1年当たり平均参入数は5倍になっています。
そのような市場環境をまとめると次のようになります。
- 生産者(農家)は大規模法人化へ向かい、従来の営農スタイルからの脱却を迫られている。
- ◇農業法人には特有の経営感覚、栽培技術力が必要で、植物工場、施設園芸では特に 栽培環境制御(気温、日照、二酸化炭素、養液管理など)での技術力が求められる。
- 農産物の安全性はますます重要になる。
- ◇農産物の産地買付け、輸出増加によりさらに安全で衛生的な農場生産管理が求められる。
- 農産物は輸入品との競争がますます激しくなる。
- ◇国内ではより低コスト、安全、高付加価値な農産物が求められる。
農業の場合は工業における物づくりと違い生産サイクルが長く、例えば米作では1年もかかります。
また、農産物は自然の環境条件に左右されるので生産調整に自由度が少ないため市場へのデリバリー体制にはより緻密な計画性が求められます。
一方品質はバラツキが比較的大きく、食べ物としての安全性は厳しく求められます。農業経営にはこのような急速な市場変化の中で競争力を維持するためは中長期的な経営ビジョンが必要です。
経営ビジョンから具体的な経営目標を設定し、全組織を効果的・効率的に運営し、目標達成に貢献するTQM(Total Quality Management:総合的品質管理)と呼ばれる管理手法があります。
主として製造業での日本企業の国際競争力を高めてきたこのTQMは汎用性が高く、農業分野にも導入することで、農業法人の経営力強化に貢献するものと考えています。
「生体認証と情報セキュリティ」
技術士(情報工学部門) 久田見 篤
銀行のATMで指先や手で本人確認を行う装置を多く見るようになりました。
近年増えているのは静脈認証と呼ばれるもので、指先や手のひらに赤外線を照射して血管のパターンを画像として取り込み、
予め登録してあるパターンと照合することで本人であることを確認します。
静脈認証以外にもスマートフォンやパソコンで指紋認証を使われている方も多いと思います。
また、2月の東京マラソンでは一部の参加者に対して事前登録した顔写真を使って顔認証によるランナーの本人確認が行われました。
あまり見かけることはありませんが虹彩や声紋を使った認証技術も実用化されており高いセキュリティが要求される場合に使われている様です。
これらの技術は生体認証またはバイオメトリクス認証と呼ばれるもので、指紋、静脈、顔などの生体的特徴や音声や署名などの行動的特徴を用いて本人であることを認証する方法です。
生体認証は本人でなければ認証されないことが最大の特徴ですが、パスワードの様に忘れたり他人に知られる心配もなく、鍵やカードの様に紛失や盗難の問題も無いなど利便性も高いと考えられています。
パスワードと生体認証を合わせてセキュリティを強化する場合や、生体認証だけで簡単に本人確認を行う場合など、今後は活用が増すと考えられています。
企業活動ではパスワードを使った情報セキュリティ管理が一般的だと思います。また鍵やカードを使った入退室制限や保管管理なども行われているでしょう。
当面は中小企業にとって個人認証を使ってさらに強固なセキュリティ対策を行う必要性は低いようにも思われます。
しかし、今後タブレットやスマートフォンなどの利用が増え、その他の多くの装置がネットワークで接続される様になると
パスワードと物理的な鍵だけでセキュリティ管理をすることは困難になるといわれています。
また個人認証はセキュリティ以外にも出退勤管理や支払管理などで企業活動における様々な合理化を支援できる技術として導入が拡大するでしょう。
生体認証には独自の課題もありますが、今後も技術開発が進められつつ実用化が拡大すると考えます。
今後の生体認証の実用化動向に注目し、企業のセキュリティ対策の強化や業務効率を向上する要素として将来に向けた検討を進めるのが肝要です。
お役立ち最新情報
[技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)

平成27年度川崎市産業振興財団との共催の技術セミナーは終了しました。 平成28年度につきましては現在計画中です。 |
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| 技術士による技術窓口相談 (無料・要予約) |
13:30~16:30 | (例)公的支援、電気用品安全法、技術・経営に関すること |
| 緊急コンサルティング(無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援致します。最大3回可能です |
| 専門家派遣(有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援 |
中小企業を応援する総合的な支援機関で、主な支援事業は次のとおりです。
★総合相談窓口 ★専門家相談窓口 ★人材育成セミナー ★専門家派遣事業
★かわさき企業家オーディション ビジネス・アイディアシーズ市場」
TEL:044-548-4141 FAX: 044-548-4146 URL: http://www.kawasaki-net.ne.jp/
NPO法人 かわさき技術士センター URL:http://www.n-kgc.or.jp/ E-mail: info@n-kgc.or.jp
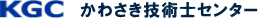
 技術支援ニュース
技術支援ニュース