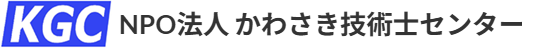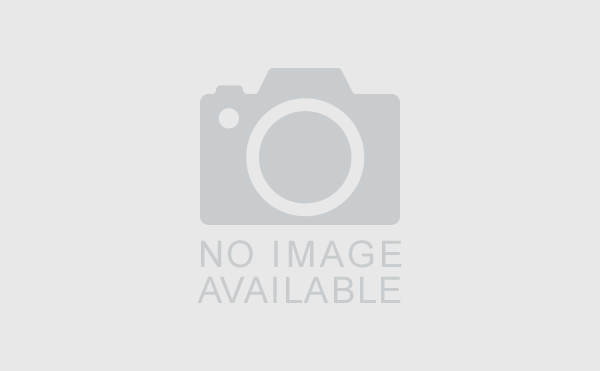中小企業技術支援ニュース第102号(2025/9)
目次
・ インクルーシブデザインの考え方
・ 隠れ食品ロスの防止
・ お役立ち最新情報
「インクルーシブデザインの考え方」 技術士(機械部門・総合技術監理部門) 嶋村 良太

近年、ものづくりやまちづくりに関連してよく耳にする言葉に「インクルーシブデザイン」があります。インクルーシブデザイン(inclusive design)は、各種の製品や施設、サービスなどをできるだけ多くの人が平等かつ円滑に利用できる「アクセシビリティ」を実現するための考え方です。
インクルーシブデザインは1994年にイギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アートのロジャー・コールマン氏によって提唱された概念で、多様な人々、とりわけ従来は製品などのデザインプロセスから排除されてきた(excluded)人々の経験や視点を取り入れて共創することで、より多くの人々にとって使いやすい製品などを目指すデザインアプローチです。年齢、性別、能力(障碍の有無を含む)、文化的背景などの多様性を前提として、デザインプロセスにできるだけ多くのユーザーを巻き込んでニーズを学び、デザインに活かすことが考え方の根幹です。
神奈川県内でインクルーシブデザインを取り入れた一例として、鎌倉海浜公園由比ガ浜地区に設けられた「インクルーシブ広場」があります。利用者や住民の声をもとに、車いすやベビーカーに乗ったまま利用できる砂場や、視覚障害者がさわって楽しむ遊具を設けるなどの工夫がなされています。
さて、同様にアクセシビリティを実現するための考え方として「ユニバーサルデザイン」があります。こちらの言葉のほうが以前から広く使われているので、なじみがある方も多いと思います。ユニバーサルデザイン(universal design)は1985年にアメリカの建築家ロナルド・メイス氏によって提唱された概念で、年齢や能力、置かれた状況などに関わらず、最初からできるだけ多くの人々が利用できる製品などをデザインするという考え方です。高齢者や障碍者を含む多様な制約を持つ人々に配慮しながら、それらの制約がない人々にとっても使いやすいデザインを目指します。
この2つの考え方を比較すると、インクルーシブデザインはデザインプロセスから排除されがちな特定ユーザーを「リードユーザー」として積極的に巻き込み、そのニーズを起点として得られた知見を広く展開してデザインを共創していきます。特定の人々の深いニーズに応えることで、結果的に多くの人々にとっても使いやすいデザインを目指します。一方ユニバーサルデザインは多くの場合、最初から「できるだけ多くの人々」を想定してデザインを進め、多様な人々を対象にユーザーテストを行いながら、多くの人が一定程度利用できる最大公約数的な使いやすさを目指します。
このようにインクルーシブデザインとユニバーサルデザインの考え方にはそれぞれの特徴がありますが、実際のデザインプロセスではどちらかの考え方だけを採用して進めればいいというわけではなく、それぞれの製品などの特性や開発ステージに応じて両方の視点を生かして開発を進めることで、より優れたデザインを実現できるものと考えます。
「隠れ食品ロスの防止」 技術士(経営工学部門) 野々村 和英
日本の食品ロス問題は、年間500万〜600万トンにもなると言われ、国全体で取り組むべき大きな課題です。私たちがスーパーや家庭で廃棄する、いわゆる「見える食品ロス」がその多くを占めます。
しかし、実はこれとは別に、統計に現れない「隠れ食品ロス」が存在するのをご存知でしょうか。
見えにくい形で捨てられている食品のことです。この「隠れ食品ロス」は年間300万トンにも及ぶと推計されています。例えば、形や大きさが不揃いで市場に出荷されず捨てられる野菜や果物、保管中に腐敗やカビで売り物にならなくなるもの、豊作で値崩れを防ぐためにやむなく廃棄されるものなどです。

これらは生産者の努力を無駄にするだけでなく、環境にも大きな負荷をかけます。食べ物を育てるには水や肥料、エネルギーといった資源が必要であり、廃棄を減らせばそれらの無駄も減らせます。特にみかんなど果物農家にとって問題は深刻です。近年は気候変動の影響で収穫時期を早め、倉庫で追熟させることが増えましたが、これが落とし穴となっています。選果前に保管された果物は小さな傷からカビが生えやすく、ひとつが汚染されると他へも広がります。防カビ剤を使っても効果が限定的で、残留基準の問題から使用を控える農家も多いのが現状です。その結果、収穫量の約3割がカビで失われる場合もあり、加工品にもできずすべて廃棄されてしまいます。この「隠れ食品ロス」を減らすため注目されているのが「空間噴霧」という技術です。ここで用いられるのが「ピーズガード」と呼ばれる安定型アルカリ次亜水(安定型アルカリ性次亜塩素酸ナトリウム水溶液)です。ピーズガードを超微細な1ミクロンのミストにして庫内に散布すると、空気中に漂う3〜5ミクロンのカビ胞子にぶつかり分解します。ミストは果物を濡らさず庫内を浮遊し続けるため、残留の心配が少なく、鮮度を保ちながらカビを効果的に抑制できます。実際の試験でもカビの広がりが抑えられ、空気中のカビ数も大幅に減少したと報告されています。さらに空間噴霧には副次的なメリットもあります。果物の鮮度保持、倉庫の嫌な臭いの除去、加工用果物の劣化防止などがあり、農家にとって収益向上につながります。従来なら廃棄していた果物が流通できれば、農家にも消費者にも大きな利点となります。「空間噴霧」とピーズガードの組み合わせは、廃棄を減らすだけでなく、農家の収益確保と安定供給を両立する持続可能な手段です。
今後は果物だけでなく、野菜や穀物、食品工場や物流倉庫などでも活用が期待され、流通段階での「隠れ食品ロス」も抑制できるでしょう。食品ロス削減は生産者、流通業者、消費者、行政が一体で取り組むべき課題です。まずは見えにくい「隠れ食品ロス」に目を向けることが大切です。ピーズガードを用いた空間噴霧のような安全で効果的な技術は、この課題を解決する大きな突破口となり得ます。家庭での工夫も重要ですが、社会全体で「隠れ食品ロス」に取り組む必要があることを、ぜひ知っていただきたいと思います。
お役立ち最新情報
[KGC(かわさき技術士センター)技術士によるセミナー] (現場経験に基づくホットな内容)検討中
◇2024年度「KIIP公益財団法人川崎市産業振興財団」との共催(技術)セミナー開催実績のご案内

第1回:「事例で学ぶ省エネ対策」~価格高騰、SDGs すべて対応します」 10月16日(水)
第2回:「事例を基にして売れる商品開発のコツを易しく解説します」 ~技術マーケティングの活用~ 11月20日(水)
時間帯:14:00~16:00/講義90分、質問30分
今後とも多くの皆様に、ご参加・ご活用頂きたく、よろしくお願いいたします。
[支援事業] (申込先:川崎市中小企業サポートセンター)
| ワンデイ・コンサルティング (無料) | 原則随時です | 企業に出向き緊急の課題を支援します。最大3回可能です。 |
| 専門家派遣 (有料) | 募集があります | 費用は半額企業負担です。課題に対し最大12回の継続支援。 |